細胞のコミュニケーションを解明する
竹内: まず、後藤さんのこれまでの研究の軌跡について聞かせてください。細胞の分化や増殖のメカニズムの研究をされている……とは認識しているのですが、その内容について具体的に解説いただけますか?
後藤: もちろんです。わたしがこれまでに注力してきた研究は、大きく2つに分けられます。ひとつは「細胞増殖・分化メカニズムの研究」、もうひとつは「神経幹細胞の運命制御メカニズムの研究」です。
前者についてですが、わたしは昔から「受精卵というたったひとつの細胞が、一体どのようなプロセスを経て、複雑な構造の生物を形成していくのだろう?」と、その謎めいた仕組みにすごく興味があったんです。先行研究では、どうやら細胞外のあるタンパク質が、細胞の核内に「増殖しろ」「分化しろ」という情報を送ることで、増殖・分化のプログラムが起動するらしい……というところまでは解明されていました。しかし、具体的にどのような経路を用いて、細胞外のタンパク質が核内に情報を伝達するのかはわかっていませんでした。
わたしは現在理研におられる西田栄介先生や仲間達とともに、その伝達に深く関わりのある酵素(MAPキナーゼ)とその活性化因子(MAPKK)を同定して、「MAPキナーゼ経路」と名付けました。このMAPキナーゼ経路は、細胞のさまざまなシグナル伝達を担う中心経路であり、酵母から哺乳類に至るまで、幅広い生物に保存されているシステムだということが判明しました。
野地: 後にMAPキナーゼ経路の異常な活性化が、さまざまながん化の原因になることもわかったことから、後藤さんの発見は医療的にも大きな意義をもつものとなりましたね。
後藤: 後者についてですが、神経幹細胞というのは、脳を構成するさまざまなニューロンと、それを支えるグリア細胞を生み出す元となる存在です。胎児の中では活発に脳の細胞を生み出しますが、成体になるとじっとしている「ほぼ働かない細胞」になります。一見すると役立たずのように見えるけれども、時が来るとすごく大事な働きをする。
そんな胎児や成体の神経幹細胞が、どんなタイミングでどのようなシグナルを受けて、秩序だって増殖・分化をしていくのか。そのメカニズムについての研究にも、これまで注力してきました。
竹内: どちらの研究でも、細胞が必要な変化を遂げていくために、どのように内外で情報の受発信を行っているのか、つまり「細胞のコミュニケーション」の仕組みにフォーカスを当てられているのですね。
後藤: まさにそうです。多細胞生物の生命のメカニズムを解き明かそうとしたとき、多数の細胞たちが内部でどんなやり取りをして、どのような影響を互いに与え合っているのかを捉えることが、とても重要になってきます。
その細胞内の構造を“社会”のように見なして俯瞰して捉えることで、初めて見えてくることがたくさんある。わたしの研究は、細胞社会で行われているコミュニケーションや情報翻訳の基本的なルールをほんの少し明らかにした、と言えるのかなと思っています。

──後藤由季子
野地: よく学生の皆さんから、「“生きている”ってどういうことですか?」と質問されることがあります。自己複製するとか、代謝するとか、いろんな答え方ができますが、「環境に適応する能力」も重要な特徴のひとつではないでしょうか。
環境に適応していくためには、外界や内部のコミュニケーションが不可欠なんですよね。外の環境からの情報を適切に受け取って、細胞間で共有し、どのように変化すれば生き残っていけるかを判断していく。お話を聞きながら、後藤さんはそんな多細胞生物の「生きる」という行為の根幹を捉えにいくような、とてもエキサイティングな研究をしているのだなと解釈しました。
「行きあたりばったり」の強さ
竹内: 「細胞の内部を“社会”のように捉える」という観点は、ぼくのような機械工学畑の人間からすると新鮮に感じます。たとえば、一般的なクルマは約3万点の部品が使われていてとても複雑ですが、同じ部品を用意して、設計図通りに組み立てれば、誰でも同じものをつくれるんですよね。
つまり、どんなに複雑なつくりをしていても、「部品」と「組み立て方」が分かれば、細胞だろうと生命だろうと複製できるのではないか……というのは、生き物を機械工学的に捉えたときの一仮説なのですが、お話を聞いていると、後藤さんはおそらくまったく違った見方で細胞を見ているんだろうなと感じました。
後藤: そうですね。人間の社会の設計図をつくろうとしても難しいのと同様に、生命の全体像はもちろん、ひとつの細胞、ひとつの遺伝子をとっても、スタティックで決定論的なイメージに還元しきることは難しいと思っています。生命はもっとゆるくて自由度が高く、動的なものと考えています。
わたしはいまゲノムの構造にはまっているのですが、遺伝子を含め、ゲノムの働きは、「AからNがある一定の距離感に集まっている」というような「場」が成立することで発揮するものが多々あります。それらは「AとB」「BとC」というパーツの組み合わせだけでは説明しきれないので、より空間的かつ動的にゲノム全体を捉えることが必要になってくるなと。
竹内: なるほど。
野地: 生命は動的だし、ゲノム配列も整然としたものではなく、結構ぐちゃぐちゃっとしてますよね。これって、生物のプログラムのコードが無計画に、場当たり的に修正されてきた結果だと思うんですよ。
いまぼくらの身体に受け継がれているものは、計画的に「これが生き残る遺伝子だ」とつくられてきたわけではなくて、たまたまある環境下で生き残った種の情報が、行き当たりばったりで積み上げられていった成れの果てだったりする。だから、人間が設計した機械やシステムに見られるような理路整然としたグランドデザインは、生命からは見えてこない。それが生命のおもしろさであり、同時にフラストレーションでもあるのですが(笑)
竹内: 確かに、一筋縄ではいきませんよね。
野地: でも、その「行きたりばったりで環境に適応していけるしなやかさ」がインストールされていることは生命の強さであり、まさに後藤さんが研究されてきた幹細胞の存在にもリンクしてきますよね。
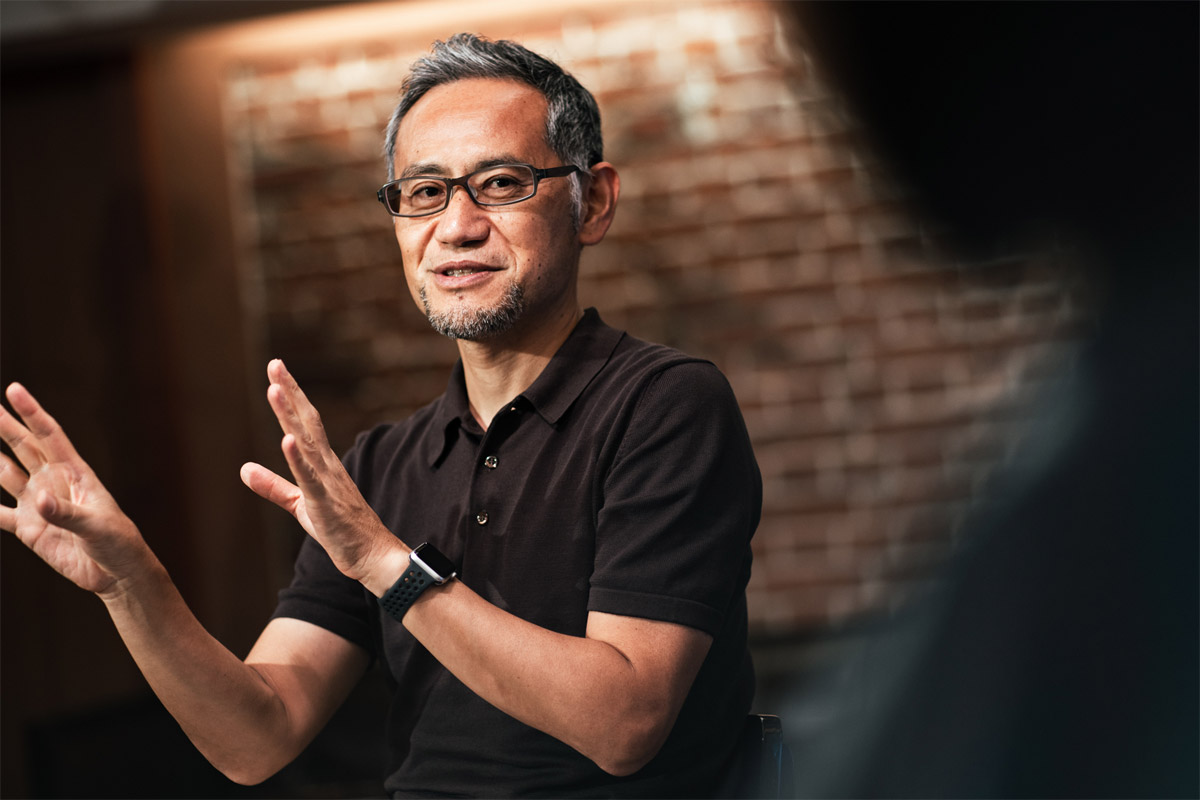
──野地博行
後藤: おっしゃる通りです。特に成体の組織幹細胞の多くは普段働かない分、有事の際に環境の変化に応じて重要な働きを見せてくれます。生命のしなやかさを支える、余白をもった存在だと思います。
竹内: 「行き当たりばったり」な設計だからこそ生まれている力強さがあると。
野地: そう、無計画に進化してきたからこそ、生物や細胞って、ものすごくレジリエントかつロバストな構造になったのではないかなと感じています。たとえば細胞の中で機能するタンパク質分子の構造を見て、「どう考えてもここが重要だろう」という要素をひとつ取り除いても、全体の機能が完全に止まることってほとんどないんですよね。抜けた要素を周りがうまく補って、なんとか動き続けるんです。そういう性質を見ると、後藤さんの言う「細胞は個ではなく場として、社会的な構造で機能する」というお話は、細胞をタンパク質分子の機能要素、社会的構造を分子の全体構造と置き換えて考えると当てはまるなぁと実感しますね。
いまこそ細胞社会から学ぶべきこと
竹内: 細胞社会のお話を聞いていると、なんだかその構造や仕組みは、人間の社会と近しい部分もあるのではないかなと感じてきました。
後藤: そうですよね。成体の組織幹細胞の多くは普段さぼっているように見えて、ここぞというときに真価を発揮します。同じように人間社会でも、普段は目立った活躍を見せていなくても、有事の際に力を発揮する人たちっていると思うんです。
野地: 人間の社会を細胞社会のアナロジーで捉えるのも、とてもおもしろいし有用な視点ですよね。人間の社会の形成過程も、歴史を振り返れば行き当たりばったりだし、まだまだ発展の途上にあるわけですから。共産主義、資本主義、民主主義と、これまでにいろいろな社会運用のかたちが発明されてきましたが、まだまだ最終的な完成形には至っていなくて、グローバルなスケールでコンペティションが続いています。
ただ、そこにはきっと常時当てはまる絶対的な解があるわけではなくて、環境や構成員のもっている能力、状態によって、その時々の最適解がある。これは見方を変えれば、「さまざまな能力や状態の構成員がいるからこそ、その時々の環境に適応できる解を見出せる」とも言えるのだと思っています。
後藤: 種全体の生存戦略を考えると、キーワードになるのは「多様性」です。たとえば細胞社会でも、みんながみんな常に全力で、現状の環境に最適化した働きをしていたら、外的な要因で環境が大きく変化したときに対応できる余裕がないために、全体が機能不全に陥ってしまうかもしれません。
わたしはいま、自閉症の方々の脳細胞についての研究をしているのですが、彼ら・彼女らが「病的」と診断されているのも、現在の環境下における価値基準でしかないんですよ。環境の変化に伴って生存に必要なパラメータが変わったら、自閉症の方々のほうが上手に適応していける未来が訪れるかもしれません。多少設計が不恰好になっても、社会に内包される要素が多様であることは、「場」が健全に存続するうえでとても大事なことだと思います。
竹内: 細胞社会でも人間社会でも、どれだけ外部環境の変化に適応して、自らを変えていけるかが、生存戦略のカギとなる。生き残っていけるよう、社会全体がロバストであるために必要なのが、多様性であると。とても納得感のある共通項だなと感じました。
ぼくも常々ラボの学生たちに「生き残るのは頭がいい人間ではなく、いち早く環境に適応した人間だよ」と伝えているんですよ。これを言っておくと、みんな新しいルールを守ってくれるので(笑)
後藤: 上手にゼミの場をコントロールされていますね(笑)
野地: 先ほど、「人間の社会は完成形に至っていない」と言いましたが、おそらくあらゆる生命についても、同じことが言えると思っています。つまり「常に未完であり、進化の余地を残し続けている状態」「進化し続けられる力」は、生命のメカニズムを理解するうえで、重要なポイントなのではないかと。
後藤: わたしも同感です。脳細胞の研究をしていると、脳がまだまだ進化の余地を大きく残していることを、ひしと感じます。そういった「進化し続ける、変化し続ける力」を発揮するための因子が何なのか、これからの研究で少しずつ明らかにしていきたいなと思っています。
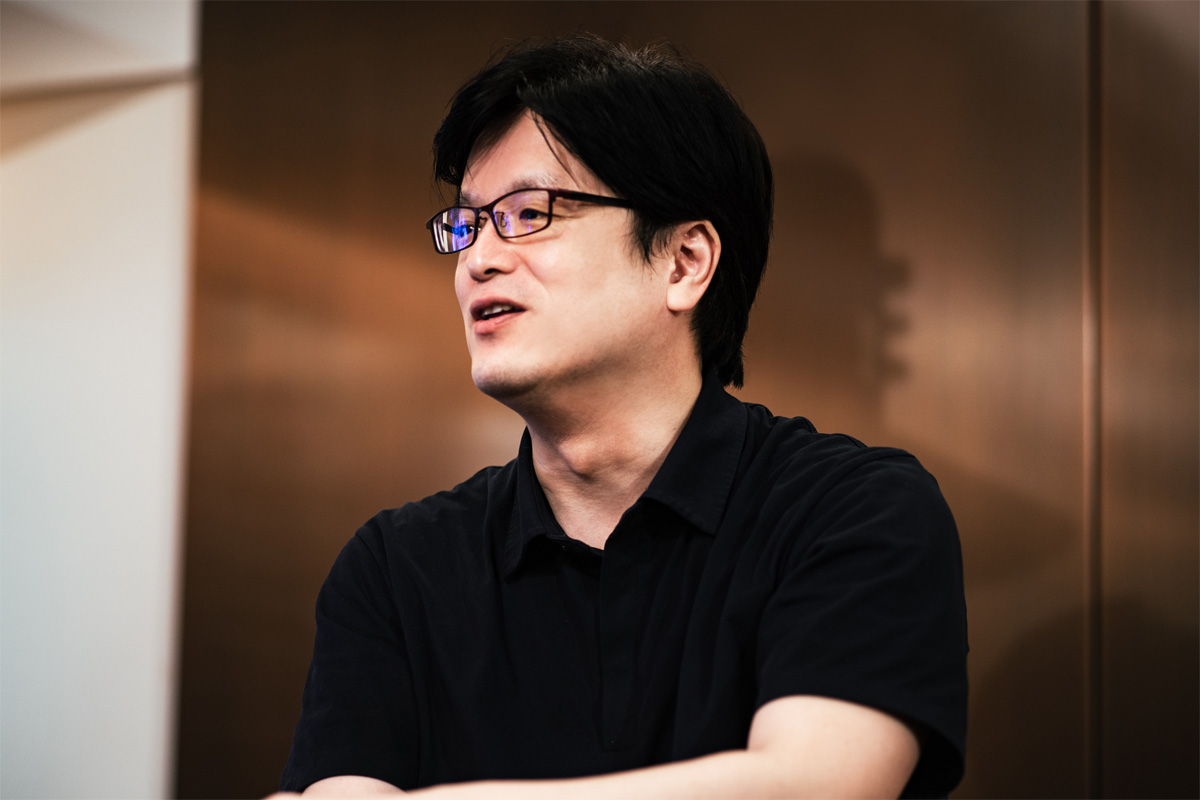
──竹内昌治
研究者は暗闇に立ち向かわなければいけない
野地: これはぜひ今回聞きたいなと思っていたのですが、後藤さんのMAPキナーゼ経路の発見は、がん治療に大きな光明をもたらしましたよね。あの研究自体、もとより医療に貢献しようという意識があったのでしょうか?
後藤: いえ、そんなことはまったくなくて。シンプルに「まだ誰も解明していない、0を1にするような研究をしたい」という知的好奇心が根底にあってスタートしたので、「こう役立てよう」といった目的意識はそれほど強くもっていませんでした。
野地: やはりそうですよね。後藤さんのような「目的意識からではなくて、当事者のエモーションで駆動する研究」が、いまの学術フィールドには切実に必要だと思っていて。UT7では、そういうエモーション・ドリブンの研究フィールドをつくっていきたいんですよね。
後藤: その思想が素敵だなと思って、わたしもUT7に参加させてもらうことに決めました。神経幹細胞にしても、いまでは移植治療や疾患治療の領域で活用するための研究が進んでいますが、元は「どうやってこの複雑な脳という組織が精巧につくられるのだろう?」「細胞社会はどんなルールで成立しているのだろう?」という純粋な興味、ワクワクに突き動かされていたからこそ、思いもよらない発見や成果につながったのだろうなと感じています。
これが、たとえば誰かから「こういう目的でこういう研究をやりなさい」と指示されたものだったりしたら、自分のパフォーマンスは最大化できなかっただろうし、いまほどの推進力のある研究にはならなかっただろうなと思います。
竹内: ぼくら研究者からすると、やっぱり後藤さんがおっしゃったような「0から1を生む研究」がいちばんやりがいがあって楽しいんですよ。ただ、「0から1」の研究は暗闇を手探りで彷徨い続けるようなものだから、自分のエモーションが乗ってないと、到底できないんですよね。
後藤: 本当にそう思います。暗闇で手探りして、あるとき扉の存在に気づき、扉が開いて次の部屋に進む、という経験を繰り返しているような感じがあります。
竹内: ただ現状の学術フィールドでは、研究を始める前に、そこに社会的な意義や創出し得る経済価値なんかを用意しないと、なかなか前に進みにくい状況がある。そういう目的ありきの研究の存在も大事だと思う一方で、そればかりになってしまうと、ノーベル賞を獲るような大きな発見は生まれなくなってしまうでしょうね。
野地: 「0から1」の研究をどれだけ生み出せるか──それこそが、UT7のカギになってくると思っています。後藤さんも含めて、ここに集まったメンバーはこれまで実際に「0から1」を生み出してきた面々です。その知見とエモーションをシェアしながら、わたしたち自身も新しい「0から1」の創造を目指し、後続の若手研究者が「0から1」に取り組みやすい環境を整えていきたいんです。
UT7の創設者である藤井さんは、「0から1を生むような研究は設計できない。ただ、それが生まれやすい土壌、文化を設計することはできるはず」とおっしゃっていました。その言葉には強く共感しています。UT7のコミュニティの輪を広げていくことで、「0から1」を生み出す文化を、ここに根付かせていきたいと思っています。
後藤: エモーションをシェアすることは大事なことだなと感じました。「暗闇に立ち向かっているのはひとりではない、仲間がいる」と思えることは、足を強く踏み出すための原動力になりますよね。
TEXT BY TAKESHI NISHIYAMA
PHOTOGRAPHS BY KAORI NISHIDA




